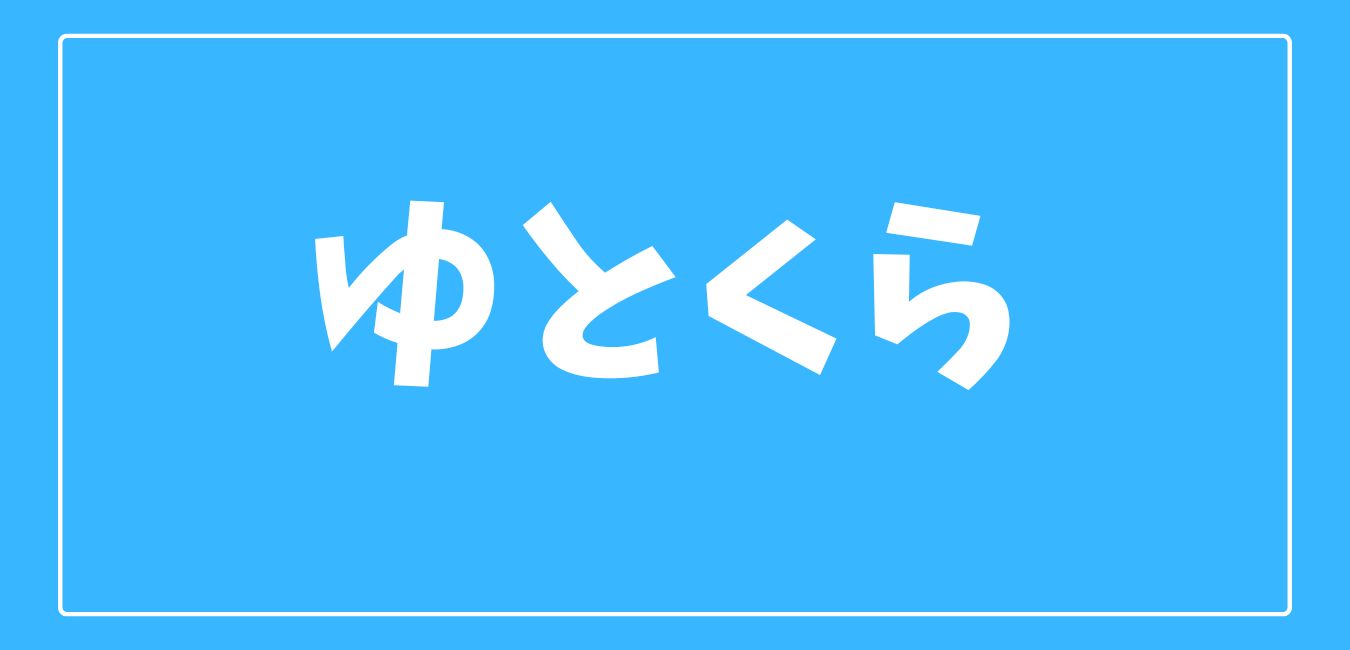ども、オーディオ大好きゆとらです。
日々ゆとり持ててる?
日々忙しく、なかなかゆとりが持てないって?
ちょっとは音楽聴く時間ぐらい持ってもいいんじゃないか?
巷では「ハイレゾ」が賑わいを見せ、高音質がやっと世間にも認知されてきた。
だがちょっと待て。
何もハイレゾでなくても、実はCDですら、とてつもない音質を秘めているのをご存知だろうか?
その音質を引き出してやるだけで、ハイレゾ並みの高音質でマッタリできるのだが。。。
今日はハイレゾはもちろんだが、CDが持つ本来の音質を引き出すための強力なアイテム「Mojo」を紹介したいと思う。
※「Mojo2」が発売される!!これは楽しみ。
CDよりレコードの方が音がイイ???
その前に「高音質ってそもそも何?」っていう、僕の体験した高音質経験をお話ししておこう。
ある事情で手に入れた古いアナログアンプでレコードを聴いたときの話。
かなり古いビートルズのレコードを聴いたときに正直オッたまげたのだ、高音質すぎて。
そのレコードの音が素晴らしく…いや、控えめに言って素晴らしすぎるぐらい最高だったのだ!
そしてレコードの音はちゃんと奥行きがあり解像度もあるのに、聴いていて全く疲れない。
何より「実在感」がCDとはレベチ!
その場でビートルズが演奏しているようで、聴き惚れて何時間もずーっと聴いてしまった。
そしてこれはビートルズ以外のレコードに変えて聴いても全く同じだった。
なのでビートルズのレコードが特別だったわけではなかったわけだ。
レコードプレーヤーもごく一般的な(というか、むしろプラスチック部品が多く使われる安い)プレーヤーだ。
目の前で演奏している・・・これはCDでは得られない衝撃体験で「完全にレコードの方が音イイじゃん!」ってその時強く感じたのだ。
オヤジ世代はCDが登場した時に「CDは音悪い」と言っていたが、その発言は【旧世代の負け惜しみ】と思っていた僕は完全に打ちのめされた。
僕がわかってなかっただけで残念ながら、事実だった。。。
実際レコードの音(というか音場感)を、CDは全く再現できていない。
確かにCDだとノイズは少ないし、耳に刺さるぐらい細かい音も出ているんだけど、何かが違う。
CDだと心が揺さぶられないのだ。
どうやったらレコードのようなまろやかで奥行きがあり、実在感のある音をCDで再現できるのだろう?
この体験が僕のオーディオに対する生涯の課題となった。
そして今の今まで「レコードの音をCDで再現するのはもう無理だろう」と、半ば諦めていたのだが。。。。
そもそも高音質って何?
先ほどから「高音質」という言葉が出てきているが、そもそも・・・
高音質とか音がイイって何だろう?どういうことだろう?
僕は、【リアルな音】が高音質だと先述の体験から感じている。
なのでCDやデジタルデータに込められた音を、可能な限り実際の音として忠実に再現できれば「音がイイ」ということになろうかと。
ところで、最近のCDに代表されるデジタル音源というのは、高解像度でノイズがなくクリアーな音なのだが、いかんせん耳に刺さって痛い感じがするのを経験したことがある人も多いのではないだろうか。
これはデータを間引くMP3とかAACなどの圧縮音源で特に顕著なのだが。
この現象はデジタルの特性ゆえ、0と1の信号として音が記録されているからとも言える。
つまりアナログ(レコードはアナログ)は途切れることなく音の波形を記録するのに対して、デジタル(CDはデジタル)は、0と1というデータとして断続的に記録されてしまう。
レコードのように音の波形がなめらかではなく、時間軸上隙間がありギザギザになってしまうのだ。
いくら細かくしたとしてもね。
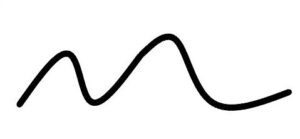

この断続的なものをなめらかにするために、デジタルの場合、実際に音にする際に「隙間を補完するフィルター」を使用している。
またアナログな波形にできるだけ近づけるために、そもそもギザギザを細かくしている=隙間を小さくしている(データ量を多くし、かつ人の可聴域外の音もデータ化している)のが「ハイレゾ」というわけだ。
 ゆとら
ゆとら44.1kHz/16bitとか192kHz/24bitとかっていう表記見たことない?
どれだけ音を細かく区切って記録しているかを表す数字だ。
人間の耳って僕らが思っているよりすごくて、このギザギザが大きい(隙間が大きい)と「不自然」と感じるようになっている。
人間には驚異的にスーパーな耳が備わっているのだ。
だから、可聴域外と言われているこういった微細な違いですら感知してしまうんだ。
高音質とは、元の音の波形にできるだけ正確に戻すことである
というわけで、デジタルはどうしてもアナログの音の波形に100%元に戻すことはできない。
逆に言うと、できるだけ正確にアナログ波形に戻せれば「自然でリアル」な音(高音質に近づく)として耳は感知できることになる。
そこで、DAC(デジタルアナログコンバーター)とかフィルターというものの出番だ。
今までの話からも、このDACやフィルターの出来が音の良しあしに大きく関わっていることは想像に難くないよね。
もちろんそれ以外にも、音を増幅するアンプとか、音を実際に発するスピーカー(ヘッドフォン)など様々な要素が音には絡んでくるんだけど。
出力される音質の大元がDACと言ってもいいかもしれない。
オーディオ好きな方なら一度は「バーブラウン」とか「ESS」とか「旭化成」のDACなんて言葉を聞いたことがあるかもしれない。
オーディオ各社は良い音を出すために高性能なDACを採用しようと奮闘している。
なので「この度、デノンは旭化成製の最新DAC「▲▲」を搭載した最新AVアンプ「〇〇」を11月より販売する。」なんてのがニュースになったりする。
根本的に考え方が違う高音質DAC「Mojo」
DACの事を少しはご理解いただけたところで・・・
一般的には各社が高音質とみなすDACほど対応kHz/bit数値が高い傾向にある。
768kHz/32bit とかそんな感じ。
ざっくり言うと、数字が大きい方がより細かくデータを変換できるとされているわけ。
それに加え、各社独自のフィルターや技術でノイズ除去や音の波形をできるだけ元の波形を再現(もしくはできるだけなめらかに)しようと頑張っている。
例えばデノンは「Advanced AL32 Processing Plus」という技術。
オンキョーの場合「VLSC」、パイオニアは「AUDIO SCALER」だったりする。
一般的に「アップサンプリング」と呼ばれているものも大きなくくりでは同じ類と言っていい。
で、こういったことが高音質の主流となる流れとは根本的にアプローチが異なる会社がある。
イギリスのハイエンドオーディオブランド「CHORD(コード)」という会社だ。
たぶん日本人にはあまりなじみのない会社名だろう。
実はオススメはそのCHORD社の「Mojo」なんだが。
CHORD社は汎用DACを使わず、「FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)」という独自のものを使って高音質化を図っている。
汎用のDACとは桁の違う膨大な計算をして、超高精度なアナログ変換を・・・なんて細かい説明はともかく。。。
とにかくスゴイ、スンバラし~!とだけ言いたい。
一応どれだけスゴイかと言うと・・・
標準的なDACと比べて
・500倍の処理性能でWTAフィルター処理(音の立ち上がりに影響)
・20倍の精度を持つ水晶発振器搭載(音の再現性に影響)
僕は「汎用DACとはケタ違いの計算をしてアナログ変換する」というこの技術に惹かれて、直感的に
「間違いなくこの技術は、昔レコードで聴いた感動する音に近づける!」
と思ったのだ。
だって汎用DACのレベルが今までどんどん上がってきて、音質アップのためにアンプをいくつか変えたりしたけれども、音の傾向はそんなに変わらなかったもの。(もちろん音質そのものは上がっているけど)
ただこういったスペックだけでは測れないのが「音質」。
トランジスタではなくスペック上の数値が劣る真空管の方が、温かみがあって良い音に聞こえるなんてのはよくある話。
Mojo音質レビューと使った感想
で、「Mojo」だよ。
これ、先述のレコード体験にはまだ及ばないけど、今までに比べかなり音の再現性が段違いなレベルだ。
んで、その割に安い!(← ここポイント)
ハイエンドな値段ではなく、一般ピーポーでも手が届いちゃう値段なのだ。
・・・っつっても、「Mojo」はポータブルアンプの分類なんだけど、ポタアンにしてはちょい高いかもしれない。
だけど性能を考えると「Mojo」は格安だと思うよ。
いくらでもお金を積めるのなら、たぶんレコード体験を再現してくれるような超弩級システムを組めるのかもしれないけど、一般ピーポーな僕にはそんな金は無いし、我が家の大蔵大臣(妻)が許してくれるハズもない。
「Mojo」はいわゆるポータブルアンプ(ポタアン)というカテゴリに属し、ヘッドフォンとかイヤホンで音楽を楽しむためのものだが、高音質に惚れて、据え置きのDACとして使用しているツワモノも、ネット検索するとたくさん出てくる。
お値段もポタアンというカテゴリのためか、約5万円とかで買えちゃう。
ハイエンドオーディオが5万円と考えると安くないだろうか?
サラリーマンでもお小遣いを貯めて、もしくはボーナスを使えば、大蔵大臣がいても何とか買えるレベルだろう。
このMojo、音の奥行き感がスゴイ。
実在感がかなりアップするのだ。
ノイズがかなり抑えられ、埋もれていた音をしっかり「再現」してくれるだけではなく、音の立体感や空気感があるのがわかる。
普段CDやiphone(ipod)などのプレイヤーで、もしくはパソコンで音楽を聴いても「大きなノイズがある」とは思えないが、実は時間軸のノイズや歪みが結構あるのだ。
ハッキリわかる雑音という意味のノイズではなくて、音をマスキングしてしまったり、立体感をなくしてしまう邪魔者がノイズと考えるとわかりやすいと思う。
「Mojo」はこういったノイズ、歪みをできる限り取り除いてくれるシステムだと思ってもらえるといい。
もっとお金を出せば更に上級機の「Hugo2」とか「DAVE」なんてのがあるんだが、お値段もスゴイことになる。
まずはオーディオ入門として「Mojo」は最良の選択肢の一つと言っていいと思う。
一つ一つの音がしっかり聞こえる上に立体感がある。
人によっては「この曲ってこんな音が入ってたのか?」という体験をすると思う。
だがガチガチの鋭く固い音ではなく、解像度が高いのにまろやかで立体感があり、空気感が再現される、という特質はレコードにも共通するものだ。
スピーカーで聴く際は、「Mojo」をUSB-DACとして、激安真空管プリアンプ「TUBE-01J」(FX-AUDIO)経由で、中古で購入した激安で古い小型アンプ(僕の場合、ONKYO「A-907X」デスクトップ横にピッタリサイズ)をパワーアンプとして使うことで、さらにレコードのような極上の音に進化し至福の時となる。
スピーカーもオークションで5000円で購入したケンウッドでも充分すぎる音質。(それなりに評価は高いスピーカーだが…)
正直「それなり」の音しか期待できないはずなのに、レコードのようにもっと聞きたくなって、どんどん音量を上げていってしまう自分に気づく。(上げすぎ注意!)
「これがほんとの高音質かぁ~」と思わず納得してニヤけてしまうほどに、まろやかかつ繊細。
僕は完全に据え置きのUSB-DACとして、そしてヘッドフォンアンプとして「Mojo」を活用しまくっている。



Mojo2買ってしまうだろうな…。
僕と同じように使う方は、付属のケーブルがあくまで充電用のものなので、ちょっとだけ、ほんとにちょっとだけいいケーブルを買おう。
これでも音質が変わるので。そう思えば安いもんだ。
USB端子が2つ以上あるPCからだと、付属のケーブルと本ケーブルを同時使用し、充電しながらMojoを楽しめるぞ。
さて「Mojo」の使用感。
筐体は航空機にも使われるアルミニウムが使われており、ガッシリ重みがあって、マットな質感が高級感を演出。
電源ボタン、音量ボタンは独特で好みがわかれるところだがLEDでカラフルさを演出してくれるため目には楽しい。
本体の熱が気になるという方もいらっしゃるようだが、夏場やや気になるぐらいで、秋~冬なんかはほんのり暖かいぐらいだ。
家でPCからMojoを通してヘッドフォンで音楽を楽しむ分には数時間たっぷり楽しめるため、バッテリーもほぼ気になったことは無い。十分に充電して使えばよいだけだ。
先ほどのオーディオ用USBケーブルを購入したなら、付属のUSBケーブルを充電専用として、充電しながら「Mojo」を使うこともできる。
ただしせっかく高音質の「Mojo」を使うのだから、ヘッドフォンで聴く場合、それなりのヘッドフォンも用意した方がいいと思う。
超高級でなくてもいいので、最低1万円以上のものを選ぼう。
おすすめは長時間の使用でも耳が痛くなりにくいゼンハイザー「HD 599 SE」。
オシャレで高音質だし、何より装着していて耳が疲れないのがいい。
アマゾンで高評価なのはもちろん、世界中の各種オーディオ誌でもゼンハイザーのこのクラスのヘッドフォンは軒並み高評価を得ている。
「ゆとりを持って音楽を聴く」には、聴き疲れ、装着疲れ、どちらも厳禁。
ヘッドフォンは頻繁に買い替えるものではないので、長く使える納得できるものを選んだ方が結局はコストパフォーマンスが高いぞ。
Mojoの欠点・デメリットは?
「Mojo」の唯一のデメリットは、更に上級機種である「Hugo2」とか「DAVE」の音質をニヤニヤ想像しつつ、物欲にかられるものの、値段が高すぎて手が出せない自分にヤキモキすることだろう(笑)。
それとバッテリーの持続時間がもっと長いとなお良いかなぁと。
それぐらいしか欠点・デメリットはなさそう。
オーディオ雑誌「HiVi」2021年夏のベストバイのヘッドフォンアンプ部門で、2015年に発売された「Mojo」が、いまだ「2位」にランクインしているのがそれを物語っている。
デメリットをメリットが上回る超ハイコスパ機と言い切ってしまおう。
あぁしかし・・・オーディオってお金がかかるね。。。
紹介しといてなんだが「Mojo」が、オーディオ沼にハマる第一歩になってしまったらスマン。
まとめ
さて「Mojo」について少しは参考にしていただければ幸いだ。
まだ「Mojo」未体験の方は一度じっくり味わってみてほしい。
またヘッドフォンアンプを検討されている方。
「Mojo」も検討に加えてみてはどうだろうか?
休日のまったりにはぴったりのウキウキ系の超ゆとりグッズだ。
毎日に「ゆとりがない」「余裕がない」と嘆いているなら、リアルで綺麗な音質がキッカケで「もっと音楽を聴こう」と思える「ゆとり」ができるかもしれない。
逆転の発想も大事だ。ワクワクや「ゆとり」を「Mojo」で取り戻そう!